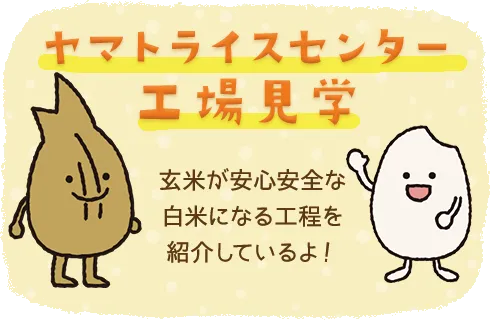【産地紹介シリーズ】山形県
普段食べているお米はどんなところで作られているの?
こちらのページではつや姫で有名な山形県の魅力をご紹介します。
山形県は東北地方の日本海側に位置する積雪の多い地域で、人の横顔のような形をしています。
日本百名山に数えられる蔵王山、鳥海山、月山などを有し、海・山・川の豊かな自然に恵まれていることから、お米や果樹、畜産が全国的にも有名です。
江戸時代には松尾芭蕉が「奥の細道」の行程のうち約3分の1をこの美しい山形県で過ごしたと言われています。

山形の寺社巡り
宝珠山立石寺(山寺)

山形の名刹「山寺」は松尾芭蕉が詠んだことでも有名です。断崖に建つ納経堂は、さながら絵画のよう。1015段の石段をのぼるごとに煩悩が消えるとされ、ゴールの五大堂では絶景のご褒美が待っています。


湯殿山神社

湯殿山、羽黒山、月山は「出羽三山」の名で知られ、古くから多くの参拝者が訪れます。
中でも湯殿山神社は「語るなかれ、聞くなかれ」、写真撮影禁止という神秘的なスポット。本宮への参拝は土足厳禁で、裸足になり御祓いを受けなければお詣りが許されません。
現在でも山伏修行などが行われている厳かなこの聖地では、俗世を離れ神の世界に触れることが出来ます。
上杉神社

軍神・上杉謙信を祀る上杉神社は、
米沢城本丸跡にあり、謙信にあやかって開運招福や諸願成就、さらには学業成就や商売繁盛のご利益もあるとされています。お堀にかかる舞鶴橋には合戦の際に掲げた「毘」「龍」と書かれた旗が出迎えます。
桜の名所としても有名で、春には米沢上杉まつり、冬の上杉雪灯篭まつりなど人気イベントの舞台にもなります。
山形の絶景ポイント

最上川舟下り
最上川は松尾芭蕉や正岡子規ら文人に詠まれた風光明媚な景色で人々を魅了しています。美しさもさることながら水路や農業用水として生活に密着し、歴史や文化を育んできたこの川は「母なる川」として県民に愛されています。
人気アクティビティの舟下りでは船頭さんの舟唄を聞きながら、鳥居に向かって糸を垂らしたような「白糸の滝」や四季折々の雄大な自然が堪能できます。

三淵渓谷
断崖絶壁の三淵渓谷はボートでしか訪れることのできない秘境です。
その昔「卯の花姫(うのはなひめ)」が身を投げ龍神となったとされる伝説の舞台で、苔むした垂直な岩壁の間に差し込む木漏れ日はまさに神秘の世界。崖上にひっそりと鎮座する三淵神社は急斜面の藪を登らなければ訪れられませんが、ボートで通ることにより参拝することができます。
狭い川幅を縫うように進むトレジャー感と、厳かな参拝が同時に味わえる貴重な体験です。

水没林(白川ダム湖岸公園)
春先から2ヶ月間だけ見られる幻想的な水没林。雪解け水がたっぷり白川湖に注がれることで次第に水があふれて周囲を覆い、水中から木が生えているように見えます。
雪が残る4月頃までは真っ白な、5月頃には新緑の水没林で来た人を楽しませてくれた後は、やがて徐々に水位が下がり元の姿に戻っていきます。

御釜(蔵王連峰)
宮城県との県境に位置する蔵王連峰はトレッキングスポットとして人気です。蔵王山頂の「御釜」と呼ばれる火口湖は蔵王のシンボルで、周囲約1kmの美しい風景が見られます。陽の当たり方や見る角度で湖面の色を変えるため「五色沼」とも呼ばれています。
湖底からは今でも硫黄物が噴出しているため、水は強酸性で生物は生息できません。
蔵王連峰は樹氷でも有名。アオモリトドマツ(オオシラビソ)が吹雪で雪と氷に覆われ、真っ白なアートを作り出します。

山形の湯

銀山温泉
レトロな雰囲気が魅力の銀山温泉。銀山川に架かる橋や、ガス燈、大正浪漫な建物がノスタルジックな気分にさせてくれます。
歩いて散策できる距離に足湯や共同浴場、土産屋、食事処から滝や鉱洞などの観光も整っているので宿泊なしでも楽しめます。

肘折(ひじおり)温泉
出羽三山のひとつ「月山」の麓に位置する肘折温泉は開湯千二百年の歴史ある温泉です。古い町並みが魅力で、特に雪の季節には何とも言えない情緒が漂います。
肘を折った老僧が傷を治したことでその名がついたと言われており、今も多くの湯治客が訪れます。春から夏の間、地元の方が開く朝市も楽しみのひとつ。
山形のお米
山形はつや姫に代表される人気銘柄の産地です。
山形は最上川やブナの原生林、雪解け水など滋養に満ちた土地で、庄内平野は平安時代からお米の産地として知られ、明治時代以降は美味しいお米が沢山とれるようにと研究が進められてきました。今では全国4位の収穫量を誇る名産地となっています。